【体験談】国際関係を学び金融業界へ!メルボルン大学修士号

森山 英雄さん | メルボルン | The University of Melbourne | International Relations
日本の大学を卒業して、メルボルン大学の国際関係修士、Master of International Relationsに進学をした英雄さん。
大学院卒業後は日本の金融業界への就職が決まりました。
国際関係分野は人気があり、日本人からのお問い合わせも多くいただきます。ご興味をお持ちの方は、ぜひ大学院進学の参考にしてください。
大学院卒業後は日本の金融業界への就職が決まりました。
国際関係分野は人気があり、日本人からのお問い合わせも多くいただきます。ご興味をお持ちの方は、ぜひ大学院進学の参考にしてください。
メルボルン大学大学院へ進学しようと考えたきっかけは?

オーストラリアの大学・大学院は教育の水準が非常に高く、かつオーストラリア自体の治安も非常によく、都心はダイバーシティが重んじられた国際都市になっており、学問に集中できると思い進学しました。
また、私は親戚に現地永住者とオーストラリア国籍の方々がおり、その方々から長年現地で生活して得た知見でサポートしていただくチャンスにも恵まれました。
学問をする上で最適なメルボルンですが、観光地としても有名であり、カフェやビーチ、伝統的な建造物など息抜きの時間にも楽しく過ごすことができます。また、テニス(オーストラリアンオープン)やFormula 1、競馬なども有名なメルボルンでは様々な楽しみ方があります。
大学の同級生が就活をする中プレッシャーを感じましたか?
私は早期の段階で海外に挑戦しようと考えていたので、周りを気にすることは特にありませんでした。むしろ、人と違うことが個性であると考える性格でしたのでその状況を楽しみながら、新たな道に挑戦できたと感じます。
メルボルン大学での勉強内容を教えてください

私はメルボルン大学の大学院で国際関係学を学びました。
国際関係学は非常に興味深い学問で、現代の世界情勢、経済、文化、政治、法律、社会的な側面に加えて、過去の具体的な事例も同様に扱います。現代の例でいえば、ロシアウクライナ戦争、NATO、米中摩擦、台湾問題、中国の一帯一路政策などがあります。
過去の事例だと、スエズ危機やウェストファリア条約、ペロポネソス戦争などです。歴史や考古学の分野とも密接に結びついていると感じます。自分が関心のある地域や国についての研究を深められる点がとても魅力的です。
リアリズムや、リベラリズム、コンストラクティヴィズムといった理論を復習し、国際法、国内法、慣習法、条約などについて再確認をします。
その後に、具体的な事例、例えば、スエズ危機であれば、クラスでチーム分けをしてそれぞれのグループがイギリスやフランス、エジプトなどを代表してディスカッションを行います。ちなみに私はソ連のグループとして発表を行いました。
各回の授業に向けて、英字論文を3冊ほど読み準備をします。1週間単位では10冊ほど読んでいると思います。1セメスターが終わる頃には、100冊以上英字論文を読んだことになります。
それでもわからないときは、独自にリサーチを行います。
余談にはなりますがこの経験で、日本に帰ったときに受けたTOEIC R&Lでは特段対策をせずに900点を突破できました。また、英語だけではなく、日本語の本も数十冊買い込んで海外に持っていき、授業の予習復習に活用しました。直近の世界のニュースをおさえておくことも授業を有意義に過ごすコツです。
最終セメスターの授業を教えてください
[火曜日]The Politics of Food(他コースからの選択授業)The Politics of Foodでは、世界的なサプライチェーンやスーパーマーケットの拡大についてリサーチをしました。
[水・木曜日]Contemporary China
こちらの授業では、中国独特のhukouシステムや台湾有事についてリサーチしました。
[金曜日]Diplomacy: Theory and PracticeとLatin America in the World
Diplomacy: Theory and Practiceでは現代における外交の多様化の側面についてフォーカスし、デジタルディプロマシーやツイッター(現X)外交の側面を研究しました。
そして、Latin America in the Worldでは、近年の中国のラテンアメリカにおける経済的、社会的、文化的な影響力の拡大についてフォーカスし、それに対してのオーストラリアの立場についてをまとめました。
印象に残っている科目を教えてください。
私が特に記憶に残っている授業は、Russia and the Worldです。2022年、世界でロシアとウクライナで戦争が始まった直後にとった授業でしたので、リアルタイムで流れてくる情報をもとにリサーチを行いました。戦争勃発から1年ほどの期間の出来事を把握し、学者の予想も考慮した上で、今後のシナリオを推測するという作業は非常に貴重な経験でした。
改めて平和の重要性を痛感したと同時に、現代においても戦争が起こり得るという現実を思い知りました。ロシアの歴史や地政学的特徴、イデオロギーの変化を学ぶことは非常に有意義でした。
Latin America in the Worldの授業も非常に新鮮でした。
ラテンアメリカの社会的な状況、特に中国との関係性について焦点を当ててリサーチしました。キューバからの特別講師が招かれる授業もありました。招待された先生が授業中に急に伝統的なダンスを踊り始めたり、楽器を弾き始めることもあり、本当にラテンアメリカを実感できる授業でした。
大学院の勉強で大変だったことは?
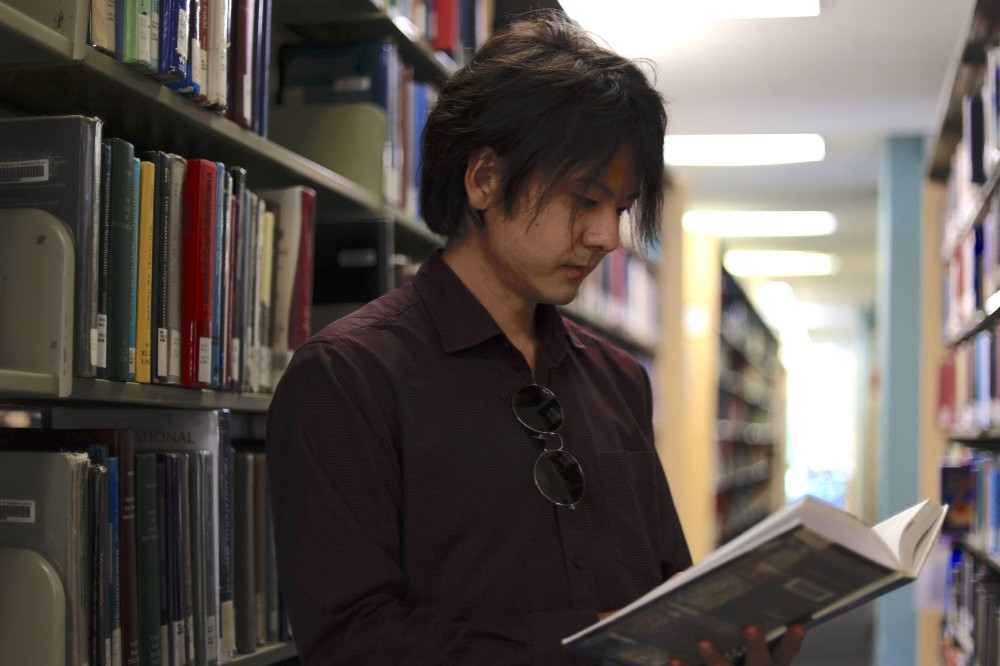
最初のセメスターでグループワークのディスカッションがあったことです。
2名ネイティブ+自分一人のグループになって、ディスカッションが全然ついていけませんでした。特に国際法関係の授業は、全然知らない分野だったのでかなり苦労をしました。
日本語のテキスト含めて勉強をして、その後のセメスターではディスカッションもしっかりと参加をすることができました。
気持ちが折れそうになることもありましたが、家族や友達に相談をして、色々とアドバイスを受けました。100%理解できいなくてもいいので、少しずつやる積み重ねが大事、というアドバイスを受けて、それを実践していました。
そして、とにかく読む量と書く量が多いのが大学院の特徴だと思います。
イメージとしては全ての学期において日本でいう卒論があるような感覚です。つまりずっと書き続けます。英語の論文や本を読むことに慣れていない間はかなりしんどいと思いますので、日本にいる間からでも洋書や英字新聞を読む習慣をつけておくと楽になるはずです。
対処法としては、1日少なくとも何ページ読むというように設定してルーティン化することだと思います。また、休憩を適宜挟んでモチベーションを維持することも大切です。
課外活動について

私は、メルボルン大学の合気道部に所属して練習に取り組んでいました。
日本で合気道をしていたわけではなく、メルボルン大学に来てから初めてでした。海外に来て、合気道という日本の文化が部活動として大学にあることに驚いたと同時に、新鮮に感じたので入部しました。
合気道では、相手の動きを利用して技を繰り出します。慣れないうちはどう動いているのか全くわからなかったのですが、現地のネイティブの師範と、日本人の先生に教えていただくうちに上達することができました。
元々10年以上、極真空手をやっていたという経験も少しは活かせているのかもしれません。
また、合気道では武器を使ったレッスンもあり、木刀を使うこともあります。その木刀をうまく攻撃に使う練習や、木刀を持ったまま、移動、受け身、回転などの動作の練習もします。
多くのことを学び、またヨーロッパからアジアまで様々な友人ができ、非常に刺激的な日々を送ることができています。
卒業後のキャリアについて教えてください
ご縁があり、第一志望の金融業界から内定をいただくことができました。祖父、父、母、共に金融の道を歩んでいたということもあり、何か特別な思いを感じています。
就職活動はマイナビへの登録と、後は気になる企業にダイレクトにコンタクトを取っていました。就職活動の時期を日本の日程に合わせて、その募集期間を狙いました。
国際関係から金融と学んだ内容とは異なりますが、メルボルン大学の大学院で培ったリサーチスキルやアナライズの知見を、将来的に業務に活かしていくことができれば良いなと考えております。また、グローバルな環境に身を置くことができた経験も、必ず活かしたいです。
メルボルン大学の良い点・悪い点

一言で表すと、どこでも学ぶことができる環境があることがメルボルン大学の1番の良いところだと思います。
まず図書館の数、広さが異次元です。
私の地元の図書館と比べると感覚的には10倍から20倍以上の広さがあると感じます。また、メルボルンは建築が発達しており、特にデザインが独特なので、様々なスタイルの図書館があり、飽きることなく場所を変えて勉強、研究に専念することができます。
大学寮も設備が充実しており、自分自身が望むライフスタイルに合わせて部屋を選択することができます。私はルームメイトの中国人やシンガポール人とよく話すことができたことが非常に良い経験になりました。
また、教授陣も世界各国から集まっており、常に知的好奇心をそそるようなレクチャーを展開しており、学生は常にワクワクしながら学ぶことができます。
レクチャーの後には自然と調和している大学内や街で休憩し、リフレッシュすることも可能です。
悪い点は特にありませんでした。
メルボルン大学大学院進学を考えている方にアドバイスをお願いします

もし英語にあまり自信がないのであれば、英会話をしておくことがベストだと感じます。
現地に行って最初に苦労したことは、ネイティブスピーカーたちとのディスカッションです。
私は、日本にいる間に英会話をして準備していきましたが、それでもやはりそこには大きな壁がありました。ですので、読み書き以上に英会話を重視した方がいいと感じます。
オンラインや対面などある中で、自分に合うやり方を見つけると良いと思います。また、現地ではとにかく、自分の意見を持って発言しようとする意思が大事であると感じます。
日本では、発言しなくてもなんとかなることもありますが、海外では積極的に発言した方が良いです。なぜならば、とにかくみんな発言したがるからです。彼らは人の意見を聞くことを楽しみにしています。
最初はネイティブの前で発言するのが恥ずかしかったり怖かったりすることも人間なのであると思いますが、少しずつ、一言ずつ発言を繰り返していくことで、その壁を乗り越えることができるはずです。
サイトのご利用について
当サイト記載の情報の正確性には万全を期しておりますが、当社はそれらの情報内容に関し、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。また、情報は予告なしに変更となる場合がございますので、随時ご確認ください。