【体験談】将来は発展途上国の教育支援に携わりたい!オーストラリアで学ぶ開発学

小林 陽さん | パース | Murdoch University | Education and Training | 1年
日本で高校を卒業して、オーストラリアに渡航した小林陽さん。現在は、開発学で定評のあるマードック大学のInternational Aida and Developmentのコースで学び、そして、オーストラリアの現地のNGOにも参加しています。マードック大学で1年を終えた陽さんに、留学体験を伺いました。
国際援助・開発コースを選んだ理由
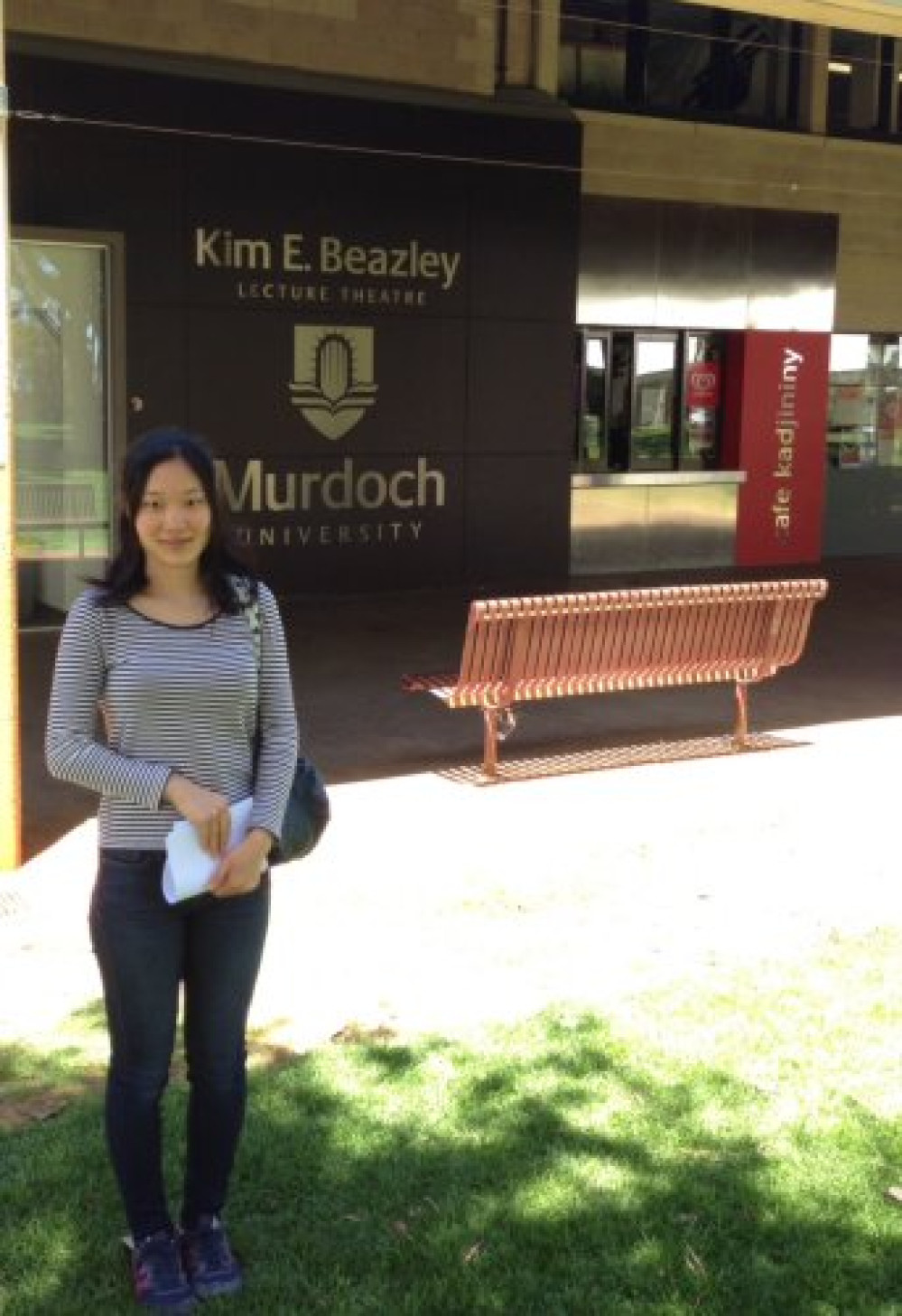
最初は、飢餓に関しての勉強をしたくて、農業を専門にしようと考えていました。でも
色々な本とかを読んでいると、国際援助や開発分野で活躍している人は、持続可能な開発等を専門にしている人が多く、このコースを選びました。
パースには元々いとこが住んでおり、パースの大学で開発学のコースを開講しているのは、マードック大学でしたので、マードック大学の開発学を選びました。
マードック大学での勉強
マードック大学は、オーストラリアで一番の敷地面積を持っており、とにかく広いです。でも、クラスや図書館、学生センター等の主要な施設は、一箇所に集まっているので授業の教室移動等は比較的楽です。大学は1学期に基本的に4科目しか受講しないので、すごく自由な時間が多いです。私の場合は、授業は週4日、全て午前中で終わりました。でも、自由な時間は多いですが、毎週全く違うトピックを勉強し、勉強量も多いので、毎週の計画を立てて、自分から勉強をしていかないと、すぐに授業についていけなくなります。
マードック大学の授業の様子
大学の授業は、講義形式のレクチャーが50分、もしくは1時間50分あります。講義といっても、先生の話しを聞く一方的な形もあれば、先生が生徒に時折質問を投げかけたり、近くの生徒とディスカッションをすることもあります。レクチャーとは別に、チュートリアルという小集団のクラスもあります。チュートリアルでは、先生がトピックを出して、グループに分かれてディベートをしたりします。チュートリアルの難しいところは、現地の大学生は自分の考えがまとまっていなくても、どんどん話をはじめるので、なかなか話に入っていけません。
考えていると、どんどん次の話題に移っていってしまいます。
15名のチュートリアルのクラスに入り、なかなか話せなかったので、先生に頼んでもっと人数の少ないクラスに変更してもらったこともありました。

大学での勉強計画
大学では、とにかく勉強量が多いです。レクチャーの内容はウェブサイトにもアップされるので、それを見て復習をしていました。ただ、次の授業の予習もしなければならず、1科目につき2~4個の論文を読み、そして、課題も出ます。課題は、記事の要約や評論、そして、私のコースでは、2週間に1つか2つレポートの提出がありました。
私は、土日月でリーディングをこなし、火水木でアサインメントをする、といったサイクルで勉強をしていました。
マードック大学のサポート
マードック大学では色々なサポート体制が整っていて、個人的なサポートはもちろん、留学生用のサポートや、1年生対象のサポート等もあり、これらを効率よく沢山活用することをお勧めします。例えば、レポートについてや参考文献の書き方(オーストラリアでは、論文の書き方は厳密に規定されています)を、先生と一対一で指導してもらえたり、同じ学部の1年生や2年生と交流する場もあります。
日本語を勉強している生徒との交流を紹介してくれるサポートもあり、こちらが日本語教える代わりに、相手の学生はレポートの文法を見てくれたりします。他にも、授業の先生にメールで質問をしても丁寧に教えてもらえますし、アポイントメントを取って直接話を聞きにいくこともできます。大学のウェブサイトはでは、教科ごとに生徒同士でディスカッション出来る場もあり、こういった場を活用すると、大学生活や勉強が充実します。

現地でボランティアへの参加
大学に入ってから、ボランティアを2つ始めました。1つは、発展途上国の子ども支援をメインにしているNGO、もう1つは、オーストラリアの難民支援をしている団体です。子ども支援のほうでは、パースの地元の学校へ行って、その団体の活動を紹介したりしています。地元の学校へ行って初めて、ローカルの10代の子たちと関わりましたが、自分よりも年下の彼らが、世界の貧困について話したりして、真剣に受け止めている姿に、意識の高さが伺えました。
子ども支援のほうは、ローカルの学生たちの英語に自分がついていけず苦労しますが、難民支援のほうは、精神的な面も関係しており、結構苦労しています。
難民支援では、難民の人たちがオーストラリア社会で孤立しないように、定期的に訪問をしてカウンセリングをしていますが、オーストラリアを拒否する人もいます。
難民としてオーストラリアにいる人たちは、自分の意思でオーストラリアを選んだわけではなく、望む/望まないに関わらず、オーストラリアに割り振られてきた人も多くいます。中には、英語は話したくない、オーストラリアの文化は嫌い、といった人たちもいます。
私が訪問をすると、「No English, No English」と言われ、ひたすら自分の国の言葉で話をされることもありました。今担当しているのは、40歳と70歳の方を担当していますが、私が行くと、「また来たの?」「早く帰らないの?」といった雰囲気が態度に出ていて、自分がやっていることに意味があるのか、考え込んでしまいます。
相手のカルチャーをリスペクトしながら、コミュニケーションを取るようにがんばっているつもりですが、心の面で相手になかなか近づくことができず、悩む日々です。
将来の目標
オーストラリアの大学に入るまでは、どちらかと言えば、「与えられたものをこなしていけば、自分の将来につながっていく」といった考えを持っていました。もちろん、それでも前進はできると思いますが、大学での生活やボランティアでの経験から、自分から行動を起こすことによってその分、出会いが増え、経験できることも豊かになり、それに比例して、より多くのことを学べて成長できるということを学びました。私は、将来的には、ストリートチルドレンや少年兵の社会復帰、女性の若すぎる結婚の廃止などの発展途上国の教育促進、支援に携われる職業につきたいと考えています。大学では、開発援助系の科目で、社会開発や支援のあり方を勉強し、コミュニティ・ディベロップメント系の科目で、様々な国の社会形成や歴史、現在の社会のあり方を勉強しています。
将来、世界中の人が努力できる環境、夢を持つことができて、その夢に向かって励める環境を実現したいので、これからチャレンジして後悔することを恐れずに、今の内にやれるべきことを考えて行動していきたいです。
※【続編】その後、大学2年生になった小林さんがアメリカの大学に交換留学しました。そのときの体験談はコチラからご覧いただけます。
スタッフからのコメント
現在はマードック大学で学ぶ陽さんですが、日本で学校に行っている頃は、英語は一番の苦手科目。最初は、語学学校で英語力をアップさせ、大学準備コースであるファウンデーションで勉強、そして、2014年2月にマードック大学に入学しました。大学での勉強は大変だけど、NGO等への参加で学生生活を充実させる陽さん、これからも応援しています。
マードック大学では、開発学の他、獣医学や医療研究やカイロプラクティック等も盛んな大学で、自然豊かなキャンパスで、リラックスして学ぶことができます(マードック大学のキャンパスについては、こちらをご参照ください)
また、ビジネスやIT系コースは、ディプロマコースからの編入プランを組むことができます。
マードック大学にご興味のある方は、お気軽にお問い合わせ下さい。

サイトのご利用について
当サイト記載の情報の正確性には万全を期しておりますが、当社はそれらの情報内容に関し、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。また、情報は予告なしに変更となる場合がございますので、随時ご確認ください。